近所の家の庭で、バーベキューが始まっていた。
香ばしい匂いと笑い声が、風にのって流れきていた。
私はまた、物欲しそうに近くをウロウロしてたんだと思う。どうしてその場にいたのか覚えてないけど、気づいたらその輪の中に混ぜてもらっていた。
大人たちは、折りたたみ椅子に体を預けて、足を組んで、ビールを飲んで、大きな声で笑っていた。
楽しそうで、きらきらして見えた。
でもその空気は、どこか冷たい感じがして、その場のにぎやかさには馴染めなくて
いいな、と思う気持ちと、自分には遠い、という寂しさが混ざって、10歳の私は胸の奥がスッと冷えるのを感じてた。
もっと楽しみたかったし、仲間に入れてもらいたいけど、なんとなく場違いな気がして、そっとその場を離れ、家に帰った。
家に戻ると、父と母は静かに体を休めていた。
テレビの音だけが流れる、静かな休日のうちの空気。それがいつもの我が家だった。
でも、さっき見た庭のにぎやかさが、なぜだかまぶしくて。派手で笑いの絶えないあの家が正解のように見えて、我が家は間違ってるような気がして「うちはダメなんじゃないか」そんなふうに思ってしまった自分に少し傷ついた。
母に「ごちそうになった」と話すと、「じゃあ、お礼にスイカを持って行きなさい」って丸ごとのスイカを手渡された。
重たいスイカ。
母が、きっと汗をかきながら坂を登って、自転車で持ち帰った我が家では夏のごちそうだ。
私はそれを抱えて、もう一度あの家へ向かった。「きっと喜んでくれる」そんなふうに思って、私なりに、あったかい気持ちを込めて、「お母さんからです」と手渡したとき、大人の男性たちがスイカを見て笑った。
「肉がスイカに化けた〜!」
その瞬間、胸の奥がズキッとした。冗談だってわかってた。でも、笑われたのはスイカだけじゃない気がした。お父さんとお母さんが一生懸命働いて買ったスイカ。
うちにとっては、ささやかだけど、ちゃんとした「贈りもの」なのに。。それを持って行った私ごと、遠回しにバカにされたような気がしてしまった。
その日から、私は「うちはうち」なんて思えなかった。むしろ、「うちはダメなんだ」と、自分で自分に言い聞かせていた。あの笑い声の奥に、私の大好きなお父さんとお母さんが馬鹿にされているような気がしてしまって深く傷ついた。
その傷は、誰にも言えなくて、言葉にならないまま、胸の奥に沈んでいった。

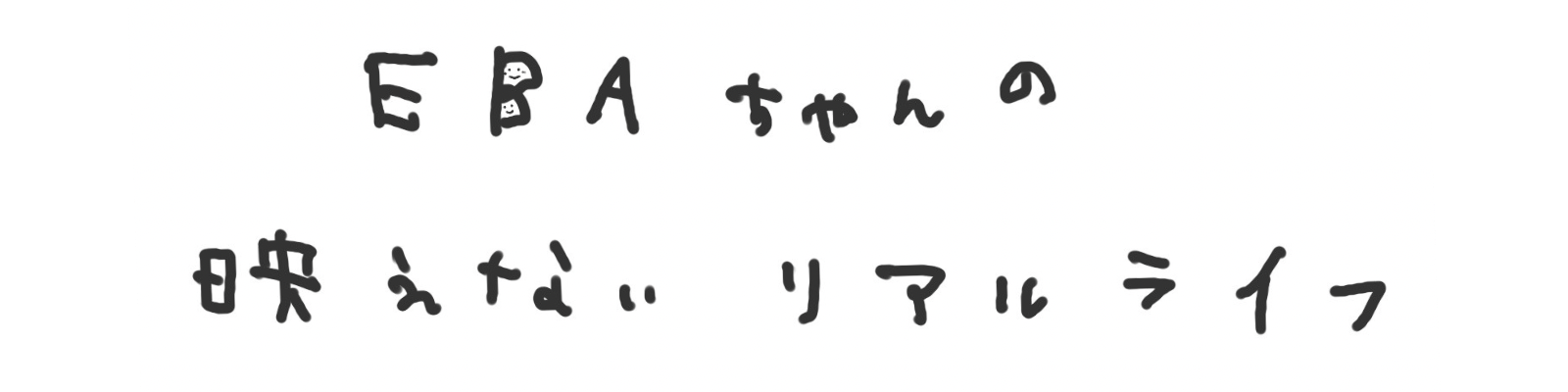

コメント