小学一年生になったばかりの春。
早い下校時間に帰宅しても、家には誰もいなかった。
共働きの両親、帰りの遅い高学年のお姉ちゃんたち。
そんな中で、毎日私の帰りを迎えてくれていたのは、三匹の猫たちだった。
たま、くま、ふんずけ。
彼らは何も言わず、ただ玄関先で私を待っていた。
小さな命のあたたかさに囲まれて、私は、なんとなく安心していた。
けれど、周りの家からは、おやつの匂いや、宿題に付き合う母親の声が聞こえてきた。
それを私は、まるで絵の中の世界みたいに、遠くからぼんやり眺めていた。
そんな日々の中、同じ町内の男の子が、毎日のように遊んでくれた。
家にランドセルを置くとすぐ、T字路の突き当たりで待ち合わせていた。
でも、不思議なことに何をして遊んでいたのか、まったく覚えていない。
おしゃべりした記憶もない。
ただ、沈黙の中に何かがあった気がする。
言葉がなくても、何かを感じていたのかもしれない。
おやつはなかったけど、私は毎回、なにかしら持って行った。
飴ちゃん一つとか、小さなおせんべい一枚とか。
それを彼に「どうぞ」って渡すのが、嬉しかった。
不器用で、うまく言葉にできないえっちゃんだったけど、渡す瞬間だけは、なぜか自信満々だった。
「どうぞ!」って顔で、パッと手渡すのが、嬉しかった。
ある日、家におやつが何もなかった。
寂しい気持ちで引き出しを開けると、そこには一万円札の束が置いてあった。
私は名案だと思った。
「これで、文房具屋さんでおやつを買えばいいんだ!」
私にとって、一万円は“お菓子がたくさん買える紙”だった。
私はその中から2枚抜き取って、いつものように彼とT字路で合流し、満面の笑みで言った。
「はい!」
言葉はたったひとこと。でも心の中は「どうぞ!」でいっぱいだった。
飴の延長線みたいに、ただ渡したかった。それが嬉しかった。
彼は、完全に固まった。
私が手渡した一万円札を、目を見開いて見つめていた。
その様子を不思議に思うこともなく、私はひとりスキップするように文房具屋へ向かった。
胸がワクワクしていた。
おばちゃんに一万円札を渡すと、レジの奥からビニール袋が出てきて、お釣りを入れて返してくれた。
たった一枚のお札が、何枚にもなって、じゃらじゃらと小銭までついてきた。
私は驚いた。増えてる。明らかに増えてる!
「減った」と言われればそうだけど、見た感じは増えてる。
だから私は「すごい!これ、めちゃくちゃ面白い!」って思ってた。
真顔で、本気で「増えたじゃん!」って思ってた。
その感覚が今も、なんだか笑えて、でも愛おしい。
でもそのあと、彼が一万円札を出した瞬間・・・
空気が変わった。
おばちゃんの声が少し高くなって、早口で何かを言っている。
内容はほとんど分からなかったけど、その声に 慌てた何か が混じっていて、私はビニール袋を受け取って立ち尽くした。
そして、その場の空気がどんどん固くなっていく中で、
私は思った。
「これ……やばいのかも……」
彼に至っては、もう逃げたそうな顔だった。
私もなんだか、いたたまれなくなって、「早く帰ろう」と思った。
でも、それでも意味は分からなかった。なぜ怒られてるのか、さっぱり分からなかった。
帰り道、私はふいに言った。
「このお金、茂みに隠そう」
2人でそっと茂みに入って、砂をかけて、ビニール袋を隠した。
なんだか、それだけで完結したような気がして、私は満足していた。
その夜には、もうほとんど忘れていた。
でも、物語は、終わっていなかった。
夕方、姉が帰ってきた。
「えっちゃん、お金どこにあるの?」
いつもの優しい声で、ふんわりと聞かれた。
怒られてないと分かって、私はホッとして、隠し場所を教えた。
一緒に歩きながら、姉は教えてくれた。
一万円札の重み、家のお金の大切さ。
言葉を選びながら、静かに、私に教えてくれた。
怒られなかった。ただ、教えてくれた。
でも、その夜。
母が帰宅した頃、文房具屋のおばちゃんが家にやってきた。
私は玄関から、門の前に立つ母の背中を見ていた。
何度も、何度も、深く頭を下げていた。
おばちゃんの声は強くて、興奮していて、母の姿が小さく見えた。
その光景が、胸の奥にずしんと響いた。
お母さんが、怒られてる。
それは、私のせいなんだ。
お母さんを、悲しませてしまった。
あの日の私は、そう思った。
母はその後、男の子の家にも行った。
でも私には何も言わず、いつも通りに接してくれた。
ただ、次の日から、彼とは遊べなくなった。
誰にも責められなかったのに、私は自分にこう言った。
「私は、ダメな子なんだ」
私は、その出来事に蓋をした。
自分でも気づかないうちに、その記憶を封じて、彼の存在さえ消してしまった。
でもそれは、蓋をしたんじゃない。心の奥に、押し込めたのだと思う。
それほどまでに、あの出来事は私の人生に、大きな影を落としていた。
わからなかっただけ。
ただ嬉しかっただけ。
なのに、私は
「生きていてはいけないかもしれない」とさえ思うようになっていった。
あの日の出来事は、私の中に小さな種を落とした。
それは自己否定と孤独を育て、何十年ものあいだ、私の根っこに、じっと張りついていた。
今日のイラスト 衝撃の現実

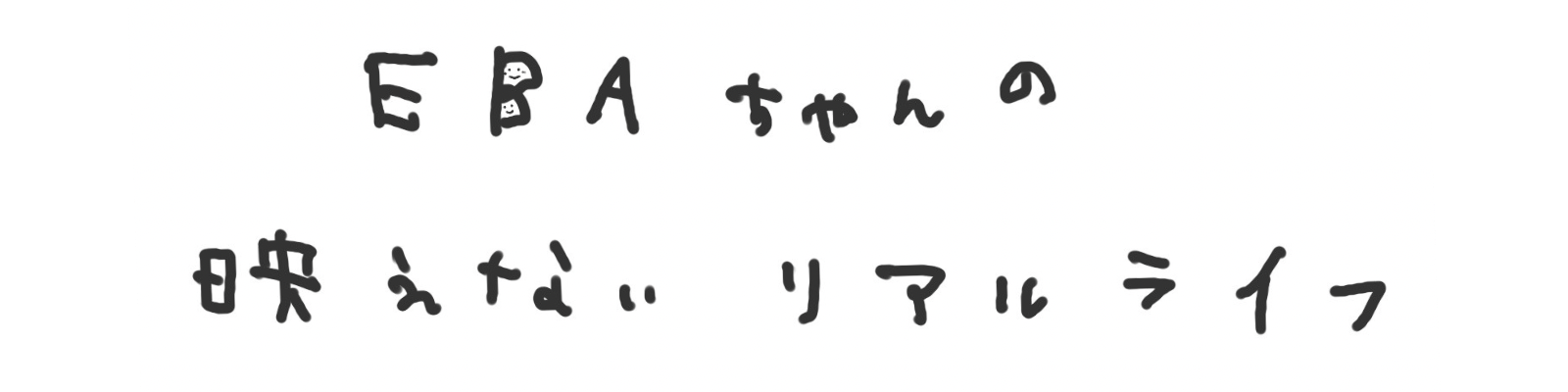

コメント