いちばん最初の記憶は、保育園の砂場。
私は、毎日のようにそこにいた。小さなスコップを持って、しゃがみ込んで、ただ黙って砂をいじっていた。
手のひらに伝わるひんやりとした感触だけが、自分の中と外をつないでくれるような気がしていた。
喋るのは、ほんとうに苦手だった。というか、どう喋っていいかわからなかった。
何を言えば正解なのか、言葉ってどう選ぶのか、順番って?子どもってもっと自由なはずなのに、私の中の「話す」という行為にはいつも壁があった。
先生に名前を呼ばれても、私はだんまりだった。母によれば、「この子、まったく喋らないんです」と心配されたらしい。
それに対して私が言ったのは、「先生が好きじゃないから」だったそうで、まあ、言い訳にしてはパンチが効いてる。
でも、ほんとのところは、好き嫌いじゃなかったと思う。私はただ、世界との距離感がうまくつかめなかったんだ。
そんなふうに、毎日、無言のまま砂場にいた私は、小さな背中で、いつも孤独を感じていた。まわりの子どもたちの声や笑いが、どこか遠くに聞こえて、自分だけ別の空気の中にいるような感覚。砂場は静かだったけど、それは心地よさとはまた違う“孤独の静けさ”だった。
でも、ある日。その孤独な静けさの中に、もうひとつの静けさが現れた。
私と同じように、喋らずに、黙って砂をいじる女の子。近すぎず、遠すぎない距離で、何日も同じように座っていた。話しかけてくることもなければ、目立つこともない。
でも、その子がそこにいるだけで、砂場の空気が少しやわらいだ。あ、この子、私と似てる。そう感じた。言葉もないのに、なぜかはっきりそう思った。
ある日、気づいたら私たちは、ふたりでひとつの砂山を作っていた。どっちから声をかけるでもなく、目配せもなく、ただ、自然に。
それは、言葉がないぶん、安心だった。自分を説明しなくても、その場にいていいと思える感覚。私の孤独が、少しだけ、やわらいでいくのを感じた。
今でもはっきり、名前が浮かぶ。
あの子と一緒に作った砂山の記憶と一緒に、その名前も、ちゃんと私の中に残ってる。
ひとりぼっちだと思っていた私の世界に、静かに差し込んできた、やわらかな光みたいな子だった。
あの砂場で感じた、無言の共鳴は、今でも、私の心のどこかで、そっと息をしている
本日のイラスト。砂場のふたり

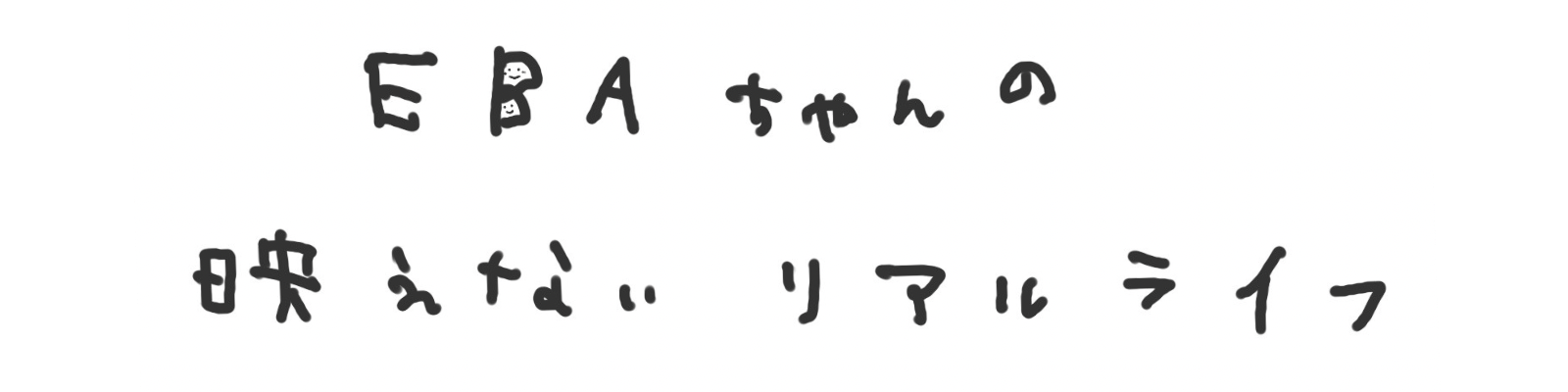

コメント