母の帰りを。父が起きてくるのを。
友達が声をかけてくれるのを。
先生が私に目を向けてくれるのを。
私は、いつも誰かを、何かを待っていた。
でも、それは苦しいことではなかった。
あの時間、私は案外、楽しかったように思う。
ブランコの上で、風と遊びながら、静かにひとりで世界とつながっていた。
キィ、キィ、とブランコの鎖の音が風に溶けていく。
夕方になると、どこかの家から、カレーの匂いや焼き魚の匂いがただよってきて、
お風呂の湯の匂い、包丁で野菜を刻む音、リビングから漏れてくるテレビの音が重なっていた。
それは、どれもが「家庭」という名のあたたかい景色だった。
その輪の中に私はいなかったけれど、なぜか、その気配を感じながらいるのが好きだった。
今日も誰も来ないかもしれない。でも、誰かが来るかもしれない。
なにかが起こるかもしれない。
そんな期待が、風の中に浮かんでいた。
私は、ひとりで待ちながら、世界の音や匂いに囲まれていた。
それが、なんだか心地よかった。
でも、ある日を境に、その時間が「楽しいもの」ではなくなった。
いつからだったか、近所の大人たちの声が耳に入るようになった。
「あそこの子、夜遅くまで1人で遊んでて……不良になるわよ」
「親はなにしてるの?」
「ほら、家庭に問題あるのよ、あそこ」
私がただブランコに乗っていたあの時間が、他人の目には「可哀想な子」「問題のある家庭の子」と映っていたらしい。
誰かに何かをされたわけじゃないのに、その言葉が、ズシンと胸にのしかかった。
私ひとりが責められているのではなくて、私の存在を通して、家族ごと否定された
そんな感覚だった。
大人たちの視線が怖くなった。
「私はおかしいのかな」「この時間って、いけないことだったの?」
楽しく遊んでいたつもりだったのに、気づけば、その時間を胸に隠すようになっていた。
「待つこと」は、楽しかったはずだった。
あの静けさも、においも、光も、私は好きだった。
でも、いつの間にかそれは、寂しさ や 孤独 という名前にすり替えられていった。
本当にそうだったのかは、今でもわからない。
ただ、あの時間は、確かに私の一部だった。
風と匂いと音に包まれていた、あのブランコの上。
そこにいた私は、間違いなく、今の私の始まりだった。
あのブランコから降りたあと、私は「自分を隠す」ことを覚えていった。
今日のイラスト ブランコ乗り

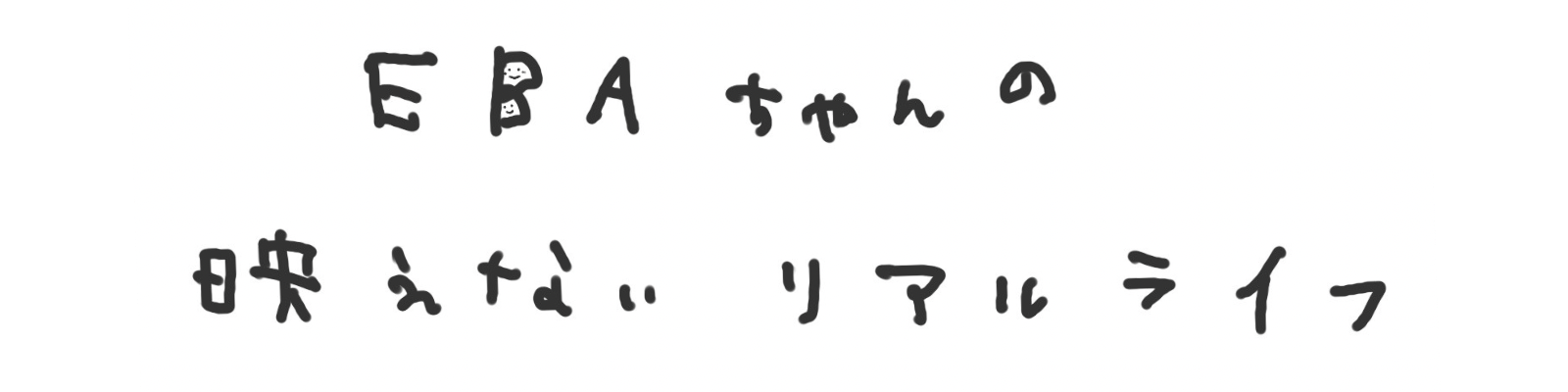

コメント